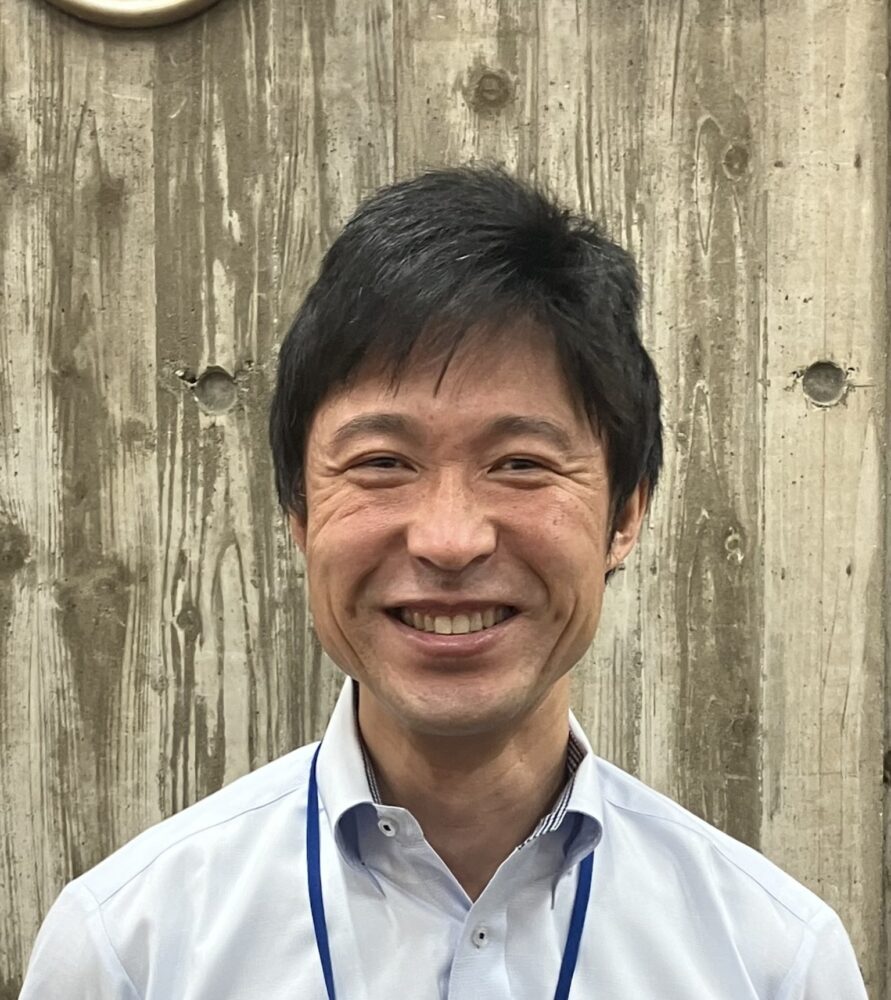電力調達の課題を解決
ESP方式で新たな選択肢が登場
従来の電力調達の方法では、どんな課題を感じていましたか?
これまでは指名競争入札で事業者を決定していましたが、社会経済情勢が不安定な中、電力の専門的な知識が乏しい状態で仕様書の見直しや適切な設計金額の設定などを行うことに、非常に高いハードルを感じていました。
そのような中、令和5年度末に契約満了を迎える高圧電力について、翌年度の契約準備を進めていたところ、ESP方式の提案を受け、信頼性の高い事業者との契約と事務負担の軽減という2つの要素に魅力を感じました。
また、万が一ESP方式で選定した事業者が倒産して電気料金があがってしまった場合でも、エネリンクが差額の補償を行うという点が、ESP方式を選択する大きな後押しとなりました。
加えて、ゼロカーボンシティ宣言をしている当市にとっては、事業者の選定基準に環境配慮の要素に取り込める点はプラス材料でしたね。
ESP方式の導入までの流れを教えてください。
当部署内で協議を重ね、ESP方式の採用を決定しました。
入札での不調を経験した後、令和5年12月から本格的にESP方式による新しい契約に向けた作業を開始し、令和6年4月からESP方式による供給がスタートしています。
50施設分を財政課が取りまとめ、相応のコスト削減効果を見込むことができるため、庁内で調整を図ることができました。
ESP方式導入の決定から実際の切り替えまでの期間は約4ヶ月でしたが、エネリンクの手厚いサポートもあり、円滑に移行できたと感じています。
コスト削減と業務効率化を実現。
ゼロカーボンシティの実現にも貢献
ESP方式を導入した効果はいかがでしょうか?
何よりも、50施設の電力使用状況を一括してモニタリングできるようになり、情報把握や予算事務がしやすくなると感じています。以前は各施設の担当者に問い合わせて数字を集めていたため作業に時間がかかっていましたが、今はWeb上で速やかにデータを入手できるようになりました。
コスト面については、ESP方式を導入して間もないため実績が確定していないものの、ESP契約の委託料を含めても約10%のコスト削減ができる見込みです。
また、実質再生可能エネルギー100%の環境メニューで電力供給を受けられることも大きなメリットです。
自治体の仕事は、最小の費用で最大の効果を上げることが求められます。ESP方式であれば、専門的な視点から最適な事業者を選定し、条件交渉や手続きのフォローまで対応してもらえるので、安心して任せられるのではないでしょうか。
一度話を聞いてみる価値はあると思います。
(取材日:2024年6月4日)